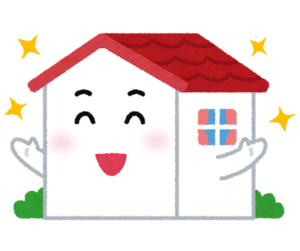新築時はピカピカの塗装が施されていた外壁も、年数を経るごとにコケや藻が発生してしまいがちです。コケの発生は外観の美しさを損なうだけではなく、住宅の機能性の低下を招くことがあります。コケの発生を抑えるには、コケが発生しやすい環境や時期を把握して、予防策を実施することが大切です。
外壁にコケが発生しやすい環境・時期
まずは、外壁にコケが発生しやすい環境や時期についてみていきましょう。
コケが発生しやすい環境
コケが繁殖しやすい環境にはいくつかの特徴があります。まず、外壁材や塗膜の劣化が見られる、もしくは塗装後2〜5年以上が経過している場合は表面が傷んで水分が浸透しやすくなるため、コケが繁殖しやすくなります。
さらに、直射日光は当たらないが明るい場所や屋根の影になる部分などは、光がある程度ありつつも湿度が保たれるため、コケにとって好環境です。また、風通しが悪く湿度が高い場所や、池・川・用水路・田園・樹木など自然環境が豊かな地域も、胞子の飛来や定着を促進します。
加えて、近隣にコケが生えている外壁があると、胞子が風などで飛ばされて自宅の外壁に付着しやすくなります。温度差が大きく結露が生じやすい建物や、外壁がザラザラしていて水が溜まりやすい場所も、胞子が付きやすくコケが根付きやすいです。
外壁にコケが発生しやすい時期
コケの種類によって、胞子をまく季節が異なります。春から初夏にかけて胞子をまくタマゴケやヒョウタンゴケは12月から伸び始め、春になると蒴柄が成長し、5月ごろに胞子嚢が成熟して胞子を飛ばします。
一方、晩秋から初春にかけて胞子をまくスギゴケの仲間であるコスギゴケは10月に成熟し、11月から翌年3月頃まで胞子を放出するのが特徴です。冬の北風はコケにとって乾燥の原因となり、繁殖を妨げる要因です。
しかし、種類によって活動時期が異なるため、コケは一年を通して発生する可能性があります。そのため、定期的にコケの除去などのメンテナンスを行うことが、外壁を守るうえで重要となります。
コケの繁殖を防ぐ予防策を紹介
外壁にコケが繁殖しにくくするためには、日頃の予防策と建材・塗料の選び方が重要です。
風通しを良くする
まず基本的な対策として、外壁の周囲に物を置いたり植物を植えたりするのは避け、風通しを良くすることが大切です。湿気がこもらないようにすることで、コケの発生を抑えることができます。
定期的に外壁の状態をチェックする
また、定期的に外壁の状態をチェックし、わずかでもコケが見つかればすぐに除去することが肝心です。最近ではコケの発生を抑制する専用薬剤も市販されているので、これらを活用するのも効果的です。
コケが付着しにくい外壁材を選ぶ
住宅の新築やリフォーム時には、コケが付着しにくい素材を選ぶことも予防策のひとつです。凹凸の少ないタイル外壁は、表面が滑らかでコケが付きにくく、さらに掃除がしやすいため非常に効果的です。
初期費用は高いものの、メンテナンス費用が抑えられるため、長期的に見るとコストパフォーマンスが高いと言えます。
コケが生えにくい特殊塗料を選ぶ
防水性の高い塗料や、コケが生えにくい特殊塗料を選ぶのもポイントです。ただし、年月が経つと外壁にひび割れが生じたり、防水性能が落ちたりするため、定期的なメンテナンスは欠かせません。
より高性能な方法として「光触媒塗料」を使うことで、雨水によって自然と汚れが流れるセルフクリーニング効果を得られます。しかし、この塗料は高価なため、予算に余裕がある場合におすすめです。
まとめ
外壁にコケが生える原因は、湿気・風通しの悪さ・外壁材の劣化など、身近な環境に潜んでいます。コケは見た目を損ねるだけでなく、建物の機能にも悪影響を及ぼすため、早めの対策が重要です。本記事では、コケが発生しやすい条件や時期を詳しく解説し、風通しの改善や外壁材・塗料の選び方など、効果的な予防策も紹介しました。日常のこまめなチェックや素材選びで、住まいの美観と耐久性をしっかり守りましょう。
 生活協同組合コープランド東京
生活協同組合コープランド東京 
 Quartet(カルテット)
Quartet(カルテット) 
 有限会社ジーワーク
有限会社ジーワーク 
 新東亜工業
新東亜工業 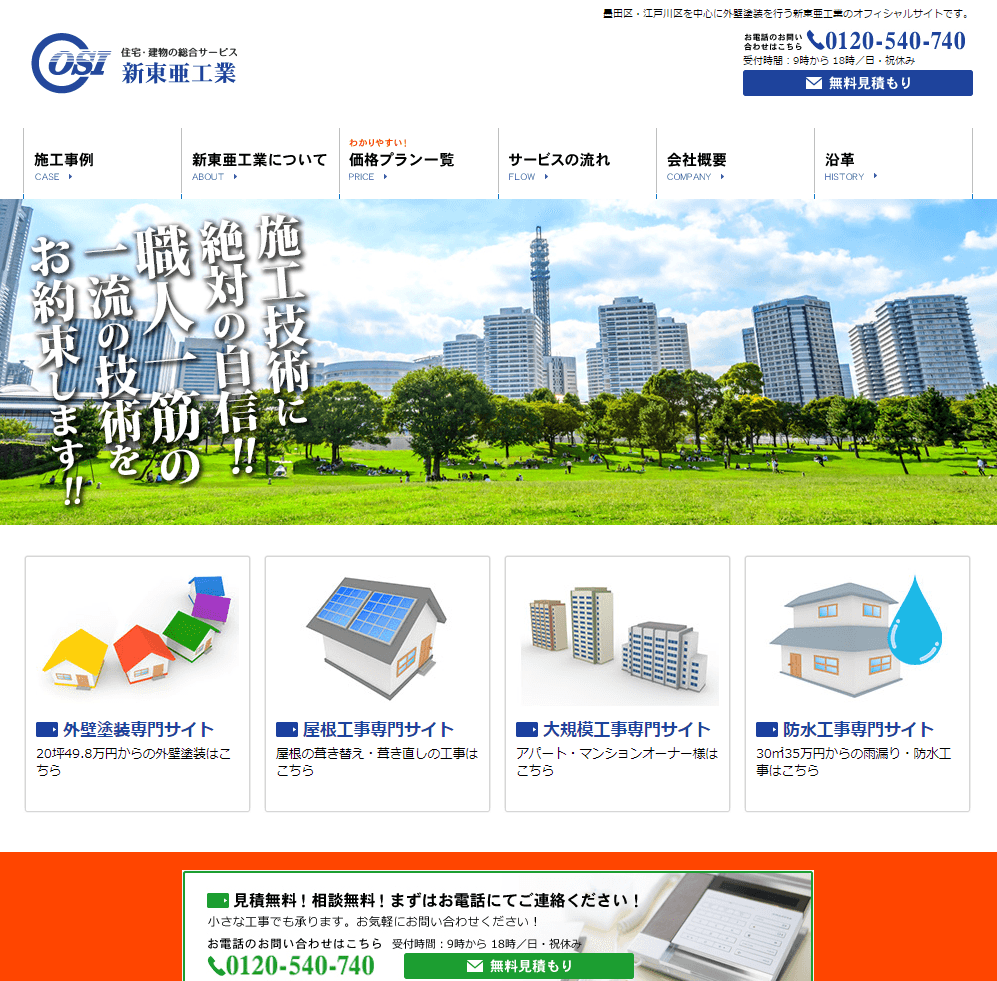
 プロタイムズ総研
プロタイムズ総研